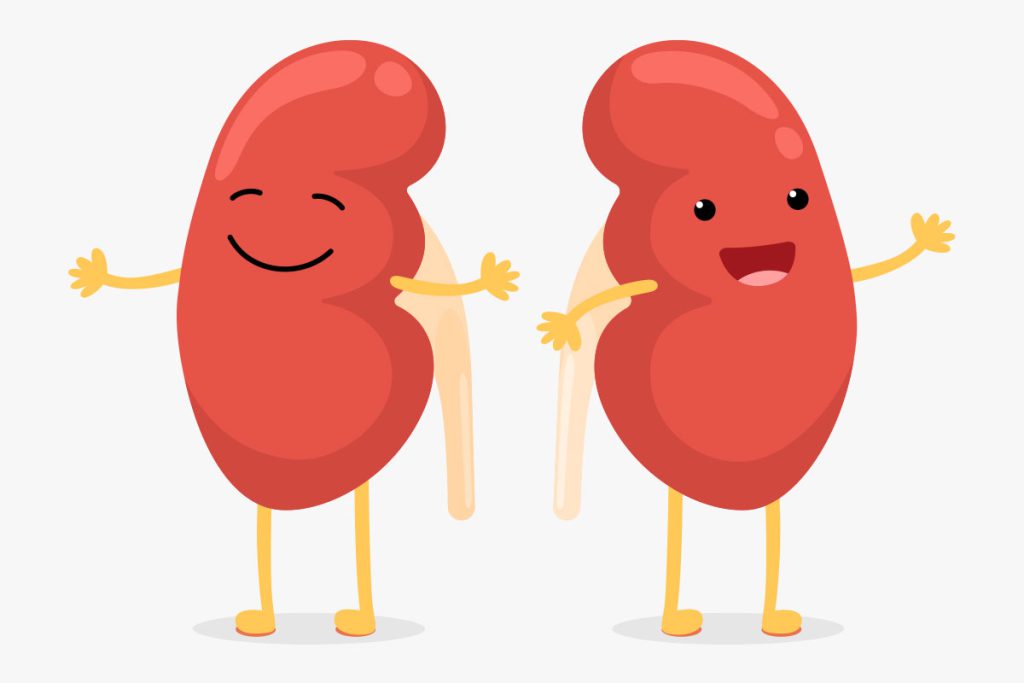
腎臓はそら豆のような形をした握りこぶしほどの大きさの臓器で、お腹の後ろ側、腰あたりに左右対称に2つあります。
腎臓はどのような働きをしているのか?
① 老廃物を体外に排出する
腎臓は血液を濾過して、老廃物や余分な水分・塩分を尿として体の外へ排出してくれます。
腎臓の機能が低下すると老廃物や余分な水分が排出できなくなり、むくみ・疲れやすい・体のだるさを自覚するようになります。
② 血圧を調整する
腎臓は水分と塩分の排出を調整することで血圧を調整しています。
血圧が高い時は塩分と水分の排出量を増やす事で血圧を下げ、血圧が低い時には塩分と水分の排出量を減らす事で血圧を上げるように働きます。
また、血圧が低い時には血圧を維持するホルモンを分泌し血圧が下がらないように調整しています。
腎臓と血圧は密接な関係があり、腎臓の機能低下により高血圧になる事があります。
また、高血圧は腎臓に負担を与え、腎臓の機能を低下させる原因になります。
③ 造血(血液をつくる)ホルモンを産生する
血液(赤血球)は骨髄の中にある細胞が腎臓から産生される造血ホルモン(エリスロポエチン)の刺激を受けてつくられます。
腎臓の機能が低下すると、造血ホルモンが産生されなくなり、血液(赤血球)がつくられず貧血になる事があります。
④ 体水分量やイオンバランスを調整する
体内の水分量・イオンバランスを調整し、体に必要なミネラルを体内に取り込む役割があります。
腎臓の機能が低下すると水分量の調節が障害され、むくみが出現するようになります。また、イオンバランスが崩れると疲れやすさ、倦怠感など様々な不調が生じる事があります。
⑤ 骨を強くする
骨の発育には様々な臓器が関与しますが、腎臓はカルシウムを体内に吸収するのに必要な活性型ビタミンDをつくっています。
腎臓の機能が低下すると活性型ビタミンDが減少し、カルシウムが吸収されなくなり骨が弱くなる傾向になります。
慢性腎臓病 (CKD: Chronic Kidney Disease) とは…

慢性に経過する全ての腎臓病を指します。日本国内で約1480万人(20歳以上の約7人に1人)※1が慢性腎臓病と推計されており、新たな国民病とも言われています。
慢性腎臓病は生活習慣病(高血圧症・脂質異常症・糖尿病)との関連が指摘されており、誰でも慢性腎臓病になりうる可能性があります。
※1 一般社団法人 日本腎臓学会編.エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023
慢性腎臓病の症状
初期には自覚症状がほとんどありません。
これが、慢性腎臓病の怖い部分で患者を増加させている原因です。放置しておくと、腎臓の機能がどんどん低下し透析療法や腎移植を行わなければいけなくなる可能性があります。
慢性腎臓病が進行すると、むくみ、倦怠感、貧血などの症状が出現します。
これらの症状が出現した段階では既に慢性腎臓病が進行している場合が多く、体調の変化に気をつけているだけでは早期発見が難しいです。
慢性腎臓病を早く見つけるには
定期的に健康診断などで血圧測定・尿検査・血液検査を受けることが早期発見につながります。
尿タンパクの出現、血液検査で血清クレアチニン値の上昇・推算糸球体濾過量(eGFR)の低下を指摘された場合には慢性腎臓病の可能性がありますので、受診をお勧めします。
生活習慣病(高血圧症・脂質異常症・糖尿病)は慢性腎臓病の予備軍です!
生活習慣病と言われる高血圧症・脂質異常症・糖尿病は腎臓の機能を低下させる要因と言われています。
生活習慣病の人は慢性腎臓病になりやすいとも言われています。
| 高血圧症 | 高血圧になると腎臓の機能は低下し、腎臓の機能低下が更なる血圧上昇を招く関係にあります。 腎臓の機能を低下させないためにも血圧管理は重要となります。 |
|---|---|
| 脂質異常症 | 脂質異常症は慢性腎臓病の発症・増悪の原因となります。 また、脂質異常が長期間持続すると動脈硬化も生じます。 動脈硬化は心臓・脳の血管疾患の原因にもなるので、脂質管理は重要となります。 |
| 糖尿病 | 高血糖状態が続いている糖尿病は、透析療法に至る原因となる病気の第1位です。 糖尿病になると腎臓の尿をつくる働きが低下し体内に余分な水分や老廃物がたまるようになります。 糖尿病の管理が悪いと腎臓の機能が低下するため、糖尿病の管理は極めて重要です。 また、糖尿病は糖尿病性網膜症を引き起こし失明に至る可能性があり、様々な障害を招く疾患です。 |


